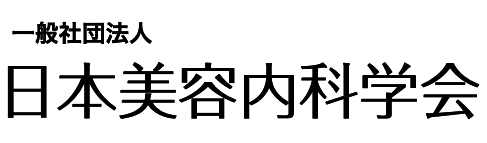美容医療において「保湿」はスキンケアの一環として捉えられることが多い。しかし皮膚科診療の現場では、保湿は明確に“治療”として位置づけられるべき行為である。皮膚は人体最大の臓器であり、外界刺激から身体を守るバリア機能を担っている。この機能が破綻すると、乾燥のみならず、炎症、かゆみ、赤み、さらには慢性的な皮膚疾患や老化の進行につながる。
アトピー性皮膚炎、酒さ、尋常性痤瘡といった疾患では、炎症そのもの以上にバリア機能低下が病態の根幹に存在する。保険診療では外用抗炎症薬や内服治療が中心となるが、これらは症状を抑えることはできても、皮膚構造そのものを再構築する力には限界がある。特に顔面では、治療後も乾燥や刺激感が残り、患者のQOLを低下させるケースを多く経験する。
そこで重要となるのが、「治療としての保湿」である。外用保湿剤による角層水分保持の維持は基本であるが、慢性的な乾燥や炎症を繰り返す症例では、それだけでは不十分なことも多い。真皮環境を整え、水分保持能そのものを改善する治療を併用することで、皮膚の刺激耐性が向上し、外用薬への反応性も改善する。結果として、ステロイドや抗炎症薬への依存度が下がる症例も少なくない。
さらに、デバイス治療による真皮加温や線維芽細胞活性化も、保湿環境の改善に寄与する。これらは見た目の改善のみならず、皮膚の恒常性を整えるという点で、美容内科的アプローチと親和性が高い。
治療と同時に欠かせないのが生活指導である。睡眠不足や慢性的ストレスは皮膚バリア機能を低下させ、炎症を助長する。また、過度な洗顔や摩擦、誤ったスキンケア習慣は、治療効果を打ち消してしまう。適切な洗浄、摩擦回避、紫外線対策、規則正しい生活リズムの指導は、皮膚治療の一部として位置づけるべきである。 美容医療は「足し算の医療」と誤解されがちだが、本質はむしろ「引き算」、すなわち炎症や刺激を減らす医療である。保湿を治療として再定義することは、美容内科が目指す「内側から整える医療」と、皮膚科医が担う「外界との境界を守る医療」をつなぐ重要な接点となるだろう。