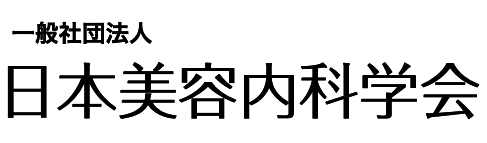2026年、医療の大きな潮流は「抗炎症」に収束していくと予測される。これまでの医学は、疾患ごとに異なる症状や臓器障害に焦点を当ててきた。しかし、慢性疾患やメンタル不調の基盤に「慢性炎症」が存在することが明らかになりつつある。糖尿病、心血管疾患、がん、認知症、うつ病といった疾患群の背景には、低レベルながら持続する炎症が共通して存在し、全身のシステムを静かに蝕んでいる。
この炎症制御の主役として、いま注目されているのが「幹細胞培養上清液」である。従来の幹細胞移植は、細胞そのものの定着や分化能を期待していたが、近年の研究で実際に治療効果を担っているのは「分泌物(セクレトーム)」であることが明らかになった。特に歯髄由来幹細胞の培養上清液には、IL-10やTGF-βといった抗炎症性サイトカインや、エクソソームを介したミクログリア調整因子が豊富に含まれ、全身の炎症ネットワークを収束させる力を持つ。
2026年は、幹細胞培養上清液が「再生医療」から「抗炎症サイトカイン治療」へとシフトする転換点となるだろう。これは単に臓器修復を超え、脳炎症を含む慢性炎症病態そのものを標的化する新しい治療モデルの確立を意味する。点滴による全身投与で、気分・認知・睡眠の改善、さらには加齢関連疾患の予防にも応用可能性が広がっている。
加えて、BHB(βヒドロキシ酪酸)や分子状水素といった代謝・抗酸化介入、求心性迷走神経刺激による神経性抗炎症反射の増強と組み合わせることで、炎症制御はより精緻なレベルに進化する。インフラマトリックスに基づく炎症源の分解とマネジメントを基盤としつつ、抗炎症サイトカインの補充・誘導を軸に据えることで、2026年は「抗炎症の年」として記憶されるだろう。